今回は2つの事件を取り上げたいと思います。
スポンサードサーチ
事件概要①
所有者兼債務者の元妻と息子が住む戸建です。
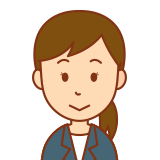
『元夫は、従前から仕事をせず、パチンコ等のギャンブルをしていて、失踪していたこともありました。彼が現在どこに住んでいるのか知りません。』
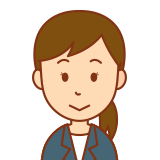
『離婚に際し、元夫は、後のことは知らないよという感じ。』
後のことは知らないよ、というセリフ通り、この家は競売され、おそらく引き渡しせざるをえなくなるでしょう。
事件概要②
所有者は80歳の女性、債務者はその元夫です。
この夫婦は、競売になる前年に離婚しています。
離婚原因は、元妻が認知症を患ったこと。
離婚の財産分与で、元妻がこの物件を取得しています。
元妻は、その弟さんが面倒を見ていたそうですが、独居困難となり、現在は施設で暮らしているようです。
こちらも、競売で買受人がいたら、引き渡しせざるをえないでしょう。
スポンサードサーチ
2つの事件の共通点は?
2つの事件の共通点は、何でしょうか?
簡単に取り出してみると、
- 離婚していること
- 離婚後、夫が出ていき、妻が家に住み続けていること
- 家が競売され、家を明け渡さなくてはならない可能性が高いこと
といったことが挙げられます。
どうして自分の住んでいる家が、競売されることになったのでしょう。
それは、その家に抵当権が設定されているからです。
抵当権とは、例えば住宅ローンを組むときに金融機関が設定するもので、「もしもお金を返せないことがあったときに、この物件を競売にかける権利」のことです。
ざっくり「抵当権を設定される」=「不動産を担保にお金を借りる」と考えて良いと思います。
今回の事件についても、住宅ローンを組んだり、事業資金を融資してもらったりして金融機関にお金を借りる際に、この物件に抵当権を設定したのだと思います。
元夫の心理は?
ここで、元夫の心理を想像してみましょう。

離婚して、家を出ることになりました。
自分が家族と住むために買ったマイホームも、今では「他人」が住む家に。
しかし、住宅ローンは自分が払っている。
…おかしくないか?
もし、自分がローンを返さなくなったとしても、もう住んでいない家が競売されるだけ。
それなら、もう払う義理はないな。
こんな感じでしょうか。
離婚後も、元妻のためにローンを払い続けるというのは、納得できないという元夫の心理も理解できないことはないです。
スポンサードサーチ
離婚時に、どうすれば良いのか?
では、元妻側の目線で、このようなことを未然に防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。
まず、大原則として覚えておいていただきたいのは『抵当権の設定されている家に住むと、競売される可能性がある』ということです。
世の中の賃貸物件の大半には抵当権が設定されています。
そして、賃貸借契約の重要事項説明の際に、その旨を説明されています。
したがって『抵当権の設定されている物件に住むな!』とは一概に言えないわけです。
ところが、今回のように無償で住む、というのは先述した元夫の心理から危険が大きいです。
そこで
- 家賃を払う
- 住宅ローンの名義を変える
といった手立てが必要だと重います。
順に説明します。
元夫と賃貸借契約を結び、家賃を払うというのはどうでしょうか。
賃貸借契約を結び、家賃を払うことで、元夫は住宅ローンなどの返済に充てられ、競売される可能性は低くなります。
ただし、元夫が生活に困ったときに、住宅ローンの支払いの優先度は低くなると考えられるため、必ずしも有効ではないと考えておきましょう。
次に、不動産の名義と住宅ローンの名義を元妻に変えるという手があります。
これは、元妻の支払い能力を問われます。
つまり、離婚後の元妻に十分な財産や収入がなくては、この手段は取れず、現実には難しいケースが多いのではないかと思います。
いずれにせよ、支払い能力のない状態で、家賃も払わずに他人の家に住むこと自体はある意味、身の丈に合っていない生活をしているとも言えるのではないでしょうか。
その場合には、自分の支払える範囲の賃料の物件に引っ越すことも考えるべきでしょう。
ちなみに、財産分与の仕方によっては、所有名義と住宅ローンの名義が異なってくるパターンも考えられますが、これは契約違反になる可能性があるので、慎重に確認しましょう。
金銭消費貸借契約の契約違反は、下手をすると期限の利益の喪失につながります。
つまり一括返済を求められるレベルの行為で、非常に危険です。
このように、元夫名義の住宅ローン等の抵当権の設定されている家に離婚後に元妻が住み続けるのは、リスクが高いです。
不動産に抵当権が設定されているかどうかは、誰でも確認できます。
登記所=法務局に行き、登記簿謄本を請求しましょう。
権利関係は、甲区と乙区に別れていますが、乙区の方で見られます。
日本の離婚率は3割程度と言われていますので、身近な問題として考えておいた方がいいと思います。
認知症の配偶者と離婚できるのか?
ここまでは、一般的な離婚後に抵当権の設定されているケースについて考えましたが、冒頭に紹介した2つ目の事件については、もう少し掘り下げることがありそうです。
こちらの事件で、元妻は認知症を患っています。
認知症を原因に離婚、という陳述がありますが、そんな事が可能なのでしょうか?
また、財産分与は適切に行われるのでしょうか?
一般に、思い病気や障害は、婚姻生活を続けるのに重大な支障をきたす事象として捉えられ、離婚原因として認められることがあるようです。
しかし、その場合、成年後見人が必要となるはずです。
成年後見人に選ばれた人にも、財産分与で得た不動産に抵当権が設定されていないか、きちんと確認してほしいものです。
成年後見人には、弁護士や司法書士がなることがあると思いますので、その際には、これらのチェックはきちんとするかと思います。
ただ、親戚などが選ばれた際に、必ずしもここまでチェックできるとは限りません。
真実は分かりませんが、超高齢社会の日本で、目を背けられない問題として取り上げてみました。

認知症になった元妻は、離婚のことを知っているのでしょうか?
そして、家が競売された事実を知っているのでしょうか?
人間の権利とは?尊厳とは?そんなことを考えさせられました。



コメント